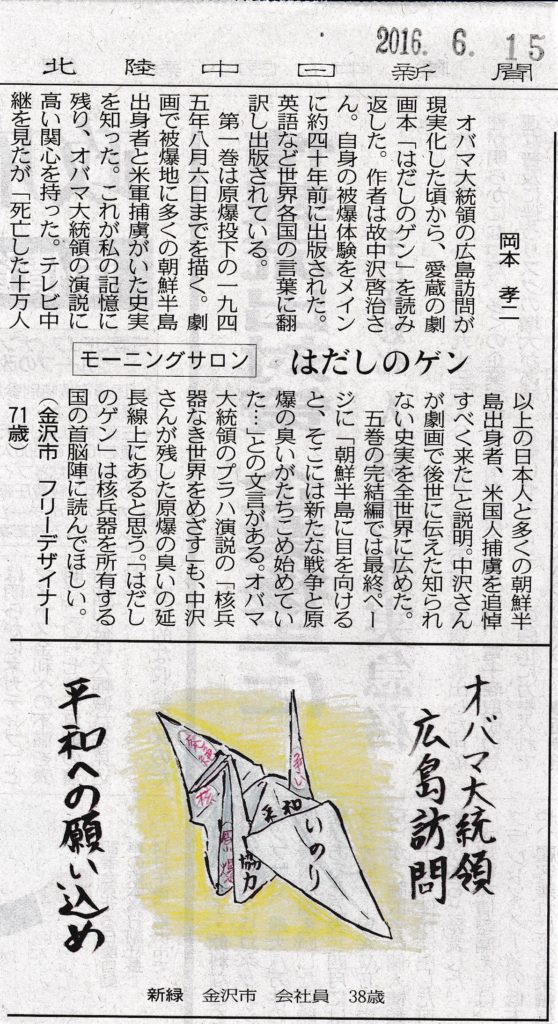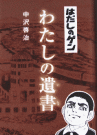毎年夏、金沢市卯辰山・玉兎ヶ丘の「平和の子ら」像前で平和を願う多くの市民が心をこめて折った折り鶴を持ち寄り、「反核・平和おりづる市民のつどい」を開いてきました。はだしのゲンをひろめる会も同実行委員会の参加団体です。
今年は被爆70年記念として、また石川県原爆被災者友の会結成55周年を記念して、被爆の実相を広く普及させるために7月26日(日)、石川県文教会館ホールにて映画『アオギリにたくして』上映会&ピースライブを開催しました。
参加者アンケートでは、「被爆した女性の被爆後の苦悩、心の葛藤、偏見、差別、悲しみ、ささやかな喜び、色々なことを映画を通して知ることができました。アオギリ二世も見に行こう。広島のアオギリも見に行こうと思います。」「大変感動的な映画でした。原爆の理不尽さとそれに立ち向かう被爆者の思いが伝わってきます。」など貴重な意見が多数寄せられました。この程反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会にて報告された「アオギリにたくして」上映会アンケート・まとめを本会ホームページに紹介します。
被爆70周年記念「アオギリにたくして」上映会アンケートの報告
■日 時:2015年7月26日(日)13:00~17:00
■会 場:石川県文教会館ホール
■企画内容 第1部 映画「アオギリにたくして」上映会
第2部 中村里美さんのピースライブ
■主 催 石川県原爆被災者友の会
共 催 反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会、平和サークルむぎわらぼうし
連絡先 石川県生活協同組合連合会
■入場者数:400人
■アンケート回収枚数:23枚
1.個人:10人
団体:石川県保険医協会、コープいしかわ、紫金草合唱団、民医連、むぎわらぼうし
2.この映画会をどこでお知りになりましたか。
①新聞などマスコミから・・・0人 ②団体からの案内・・・8人 ③知人から・・・11人
④その他・・・沖縄の写真展(6月)のチラシを見て。
3.映画の感想をお書きください。
・あっという間の2時間でした。「こんな現実が実際にあったのか、わずか70年前の日本で?!」ということを改めて実感し、身震いがしました。あの時の過ちを二度と繰り返してはいけない。若い私たちは経験していない分、伝えていかなければいけない責任を負っていると思います。多くの人々に是非観ていただきたいと思った映画でした。
・たった70年前のことを私はちゃんと知らない。人にもっと伝えていけるように一人ひとりが原爆のこと、戦争のこと、平和を守るために何を守っていけばよいのか、考えていけるように、もっとたくさんの人に観てほしいと思いました。
・試写会と合わせて2回観て、改めてこの映画の訴える声の大切さに気付かされました。同じ被爆者の間でも差別し差別されてしまう現実、悲しさ、そんな大変な目に合いながらもいくつもの障害を乗り越え、語り部として生き抜いた主人公の生き方に心を動かされました。
・小学生の時「ヒロシマ」の映画を観て大変ショックを得ました。その後、何度もヒロシマに関する映画を観てきましたが、今回の映画「アオギリにたくして」は、戦後ずっと被爆者の方が人生の歴史を背負って伝える、語り部の熱く、苦しく、辛い思いを世界の全ての人々に伝えるべく映画として本当に感動しました! 最近出なかった涙が一杯溢れ出るものでした。
・「被爆者が被爆者を差別する」現実があったことは大きな衝撃であり、心に残った言葉でした。原爆の悲惨さを伝えて余りある内容ですね。製作された方々に感謝しなければなりません。
・素晴らしかった。広島の人々の苦しみは私たち被爆していない者の想像を絶するものだった。
・田中節子さん、まさに芽吹いた被爆アオギリのように強く生き抜いてこられた人生だったのだとよくわかりました。小5の娘にも理解できたようでした。娘は学校の図書委員会で「すみれ島」の朗読をするそうで、8/6も平和集会でアオギリの歌(今日の歌とは違う)を合唱するそうです。今日の映画を観れたことで、娘の中に平和への想いや願いの層が少し増えたかな。「この子たちの夏」の朗読劇は、まだ娘は知らないけれど、いつか出会いたいな。今日の映画、被爆後の苦難の人生を生き抜いてきた一人の女性の物語を無名のライターである一人の女性が取材し、形にしていくという「つなげていく」ことの大切さをメッセージとして受け取りました。ありがとうございました。
・ヒバクシャ同士でキズつけ合うのは悲しいなと思いました。もし私が節子さんだと耐えられないなと思いました。(小5)
・語り部の存在を伝え続けることの大切さ、辛い体験を証言した語り部の声を聞くことができて感謝。
・人は誰も皆幸せに生きる権利を持つ、何者にもそれを阻むことは許されない・・・節子と隆志はなぜ幸せになることができなかったのかと考えるなら戦争や原爆がない社会にまで戻らなければならない・・・。声高にではなく静かに、然し心の深くまで届いたメッセージです。観てよかった、みせてもらってありがとうございました。
・もう2度と戦争起こしたらいかんね。70年たった今も辛い人がいるんだもんね。これからも戦争の悲惨さを伝えていかんなんね。
・主人公の心情を中心に描かれていたのが良かった。
・被爆した女性の被爆後の苦悩、心の葛藤、偏見、差別、悲しみ、ささやかな喜び、色々なことを映画を通して知ることができました。アオギリ二世も見に行こう。広島のアオギリも見に行こうと思います。
・原爆体験者は、原爆時の体験はもとより、それ以後が壮絶な戦いであったことがよくわかった。被爆者が被爆者を差別する、そんな状況を作りあげる、それが戦争だ。
・大変感動的な映画でした。原爆の理不尽さとそれに立ち向かう被爆者の思いが伝わってきます。
・試写も観ましたが今回の方が良かったです。
・本日は被爆者の方の新たなメッセージとして「アオギリのように生きていかなければならない」という言葉が心に残りました。
・静かであたたかく、力強い映画でした。観てよかったです。
・沼田さんの人生をじっくりとたどらせていただき、とても心揺さぶられました。
・罪のない人たちが犠牲になる戦争は絶対に許せない。二度と繰り返してはいけないことと改めて思いました。風見しんごさんのファンなので見れて嬉しかったです。
・被爆して、差別と偏見の中で被爆者は生きてきた。放射能でどんな影響が出るかわからない、と差別され、どんな影響が出るかわからないと不安を感じ、大丈夫心配ないと言われ、どういうことかわからなくなりそうだけど考えてきた人。
・感動した。
・いい映画でした。
4.ピースライブの感想をお書きください。
・歌いやすい曲、心に迫る朗読がとーっても良かったです。やっぱり歌は会場の皆さんと一体になれる素敵な手段だなと思いました。歌を覚えていろんな場面でいろんな人々に歌って広めたいなと強く感じました。幸せな時間をありがとうございました。
・歌もギターも心に強く響き、とても良かったです。CDを買い自宅でも聴いています。
・映画と連動するものだっただけに、多くを語らずともよく理解できるもので、静かに聴くことができました。
・歌でも平和を伝え続けていけることに心をうたれました。
・体験の話、歌を通じて~、広島や長崎で起きたこと、伝えていきます。
・中村さんの想いが伝わった。
・プロデューサーの中村さんや伊藤さんの言葉は、わかりやすく重みがありました。中村さんの「伝えなきゃ」「伝えたい」という使命感がひしひしと伝わってきました。歌も良かったけど朗読も良かったです。
・歌の力を実感しました。メッセージが良く伝わりました。
・原爆体験を21歳の時に聞き、その思いを29年間行動されてきた里美さんの優しい歌声と強いメッセージを感じました。
・うちの娘(小4)が学校で習ったと言っていつも口ずさんでいる歌が、まさかここで聴けるなんて!?「平和の子ら」の歌です。どの歌ももっと多くの人に聴いてもらいたい。いい曲です。
・体験していない世代が、受け止めて、伝えることがこれから本当に大事になっていると思った。
・草の根の活動が支えていることがよくわかった。
・こういう取り組みを続けてほしい。ここにいると勇気が出るが、この場で終わらせてはいけない。
・内容的には良かったが、映画が長かったのでこの部分はまた別の機会に(プレ企画etc.)回すのがよかった。第一部終了後、帰った人が多く残念でした。
・素敵な歌声をありがとうございました。
・一緒に歌えて良かったです。
・久々に歌いました。
・「でえげっさあ」が2人しかいなくて残念でした。
5.今後の平和の取り組みでしたいこと、企画してほしいことをお書きください。
・子どもたちへの絵本(平和に関する)の読み聞かせ。
・子どもたちへの伝言、過去をきちんと伝えること。学校での取り組みが鍵だと思う。
・若い人、子どもたちをターゲットにしたもの。
・アオギリ二世を小学校に植えたい。8月6日の小学校の登校日がなくなってしまったことを残念に思う。
・アオギリの木を植えていく活動はいいなと思いました。(小5)
・今回のようにいろんな人、年代の人たちが気軽に参加できる企画をお願いします。
・今日みたいな上映会や伝えていく機会を作ってほしい。
・ピースライブはいいと思います。朗読会なども。吉永小百合さんの朗読会をライブで聴いてみたいです。
・広告、宣伝、多くの人の目に見える形で平和を考えたい。バスとかフォーラスなどの大型ディスプレイとか。
・映画、演劇、その他。
・卯辰山よりも天気を気にせずに集まれるので、またここでこの様な会があるといいなと思いました。
6.平和へのメッセージなどお書きください。
・戦争に「ヒトゴト」ではなく、危機感を持ちながら今後の日本のいく先に関心を向け続けたいと思います。考えることを、声をあげることをやめたくない。何気ない日常生活を笑って過ごせることが何よりの「平和」だと思っているから。
・子どもたち、孫たちにずっと平和な世の中を手渡し続けたいです。
・平和の大切さ、周りの人たちに私なりに伝えていきたいです。
・平和のために自分ができることを続けていきたい。
・自分でできることを小さいことでもいいので何でもしたい。まずは子どもたちに話していきます。
・あなたも私もかけがえのない大切な存在、と世界中の人々が思えたら争いはなくなると思います。
・自分のできることはちっぽけだけど、あきらめず、卑屈にならず、人間を信じて、平和な世界を求め、声をあげ、種をまき、まず身近な人との会話の話題にしていきたいと思います。無理せず、気負わず、細くても長く続けていきたいと思います。
・絶対に戦争させない。全ての人が平和の中で幸せに生きられるように。
・(広島でさえ平和を考える機会が減っている)戦争の悲惨さ、原爆のもたらした被爆の現実を未来に伝えよう。過去を直視できない人間に未来はない。
・平和が続くために・・・ 原発、核兵器、戦争は絶対なくそう。
・平和憲法の重み、意義、その力を広めていきたいです。
・司会の小原さんも良かったです。その言葉に込められた訴え、戦争を許さない。安倍を許さない!子どもたちのために、心を込めて。
・憲法違反と考えられる集団的安全保障法案は憲法裁判にかけることはできないのか。一歩一歩戦争の雰囲気に近づいている気がする。
・「アベ政治を許さない!」戦争法案は廃案にしよう!
・戦争法案反対!原発再稼働に反対!みんなで力を合わせて頑張りましょう!未来の子供どもたちのために・・・!
・憲法を守り平和を守り続けたいです。
・平和を希うすべての人たちで力を合わせ、できる限りのことをして安保法案を何としても廃案にしましょう。
・この法案を止めましょう!